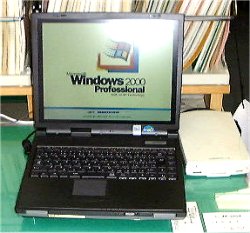システム不安定
使用している間にはやはりトラブルでマシンがフリーズしてしまうことがあります。Win9Xに比べると再起動しなければならないほどの事態になることは少ないのですが、ときにはCTRL+ALT+DELETEが効かなくなることもあります。そんなことを何度か繰り返しているうちに、動作が少しずつ不安定になってきました。そこで思い切って再セットアップしようか、と決心してリカバリ用のFDで起動してみると、「修復セットアップ」というのがあります。これはいいということで早速やってみました。アプリケーションの再インストールまで覚悟していましたが、これでその必要もなくなりました。しかし、やはりこれでは完全ではありませんでした。以前よりは良いものの、起動や終了時に異常に時間がかかったりします。
|
 |
HDD換装?
そんなことから、思い切って完全に再セットアップしよう、と思うのですが、環境を再構築することを考えると二の足を踏んでしまいます。特に日本語P-LaTeXの環境設定がログイン名によってうまくいかなかったりして(一番最初に「Administrator」でインストールしてきちんと動作しているのに、通常使用しているログイン名ではうまく動作しない)、これがうまくいくかどうかが一番心配です。
そこで考えたのは新しいHDDに再セットアップして、いざという場合は今のHDDに戻す、ということです。デスクトップ機は過去にいろいろいじっていたし、すでに自作も経験(2台)していますが、ノートパソコンを分解するには勇気がいります。しかし、いろいろ調べてAsusutecのベアボーン型ノートパソコンと基本的に同じ構造であることから、HDD換装の仕方を見つけることができました。いつやるかわかりませんが、とりあえずHDDをはずすというところまではやってみました。 |
やってみれば簡単です。底のネジを3本はずし、パームレストの部分を手前にスライドさせると右側にHDDドライブがあります。通常のノート用2.5インチHDDが金属製のカバーで固定されていますから、それをはずして新しいドライブに変えればOKのようです。デスクトップ用3.5インチHDDに比べるとまだまだ高価ですが、そのうちやるような予感がします。 (写真上パームレストをはずし、ハードディスクを取り出したところ) 2001.7.3
|