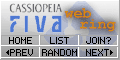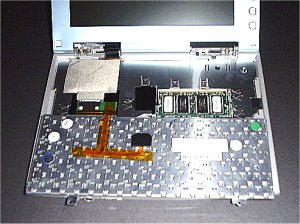★ ★ ★ HDBENCH Ver 2.610 ★ ★ ★
使用機種 Cassiopeia FIVA MPC-205
Processor Crusoe 497.4MHz [GenuineTMx86 family 5 model 4 step 3]
解像度 800x600 65536色(16Bit)
Display Silicon Motion Lynx
Memory 113,732Kbyte
OS Windows 98 4.90 (Build: 3000)
Date 2001/ 6/16 20: 2
HDC = ALi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)
HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)
C = IBM DJSA-210 |
| ALL |
浮 |
整 |
矩 |
円 |
Text |
Scroll |
DD |
Read |
Write |
Memory |
Drive |
| 12363 |
24467 |
27992 |
14812 |
3046 |
13186 |
171 |
14 |
6606 |
8625 |
21267 |
C:10MB |
|